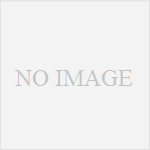環境問題は深刻な状況
2009/9/28 アジア(環境・自然), ヨーロッパ(環境・自然), ヨーロッパ(社会), 環境・自然, 社会
CO2, GDP, IEA, アジア(戦争・紛争), ウラン, エネルギー, クリーン, スウェーデン, スペイン, フォロ・ヌクレアール, フランス, ヨーロッパ(戦争・紛争), ワールドウォッチ研究所, 中国, 二酸化炭素, 化学物質, 化石燃料, 原子力, 原子力エネルギー, 原子力発電, 原子力発電所, 原子炉, 地球, 大気汚染, 天然ガス, 排出量, 放射性廃棄物, 放射線物質, 次世代型原子炉, 欧州委員会, 欧米, 水, 水力, 温室効果ガス, 温暖化, 火力発電所, 環境, 発展途上国, 石油, 石炭, 米国, 経済, 自然環境, 英国, 電力 谷口 永治
関連記事
時代を変える移民(From Newsweek 2009.4.1)
「倫理潔癖性が生む空っぽの政権」 エバン・トーマス、ジョン・バリー(ワシントン支局) 米オバマ政権に世界が熱狂してから、もう4ヵ月...